あなたの家のルール、もしかしたらヴァナキュラーかもしれません
- クリティカル・ライティングゼミ
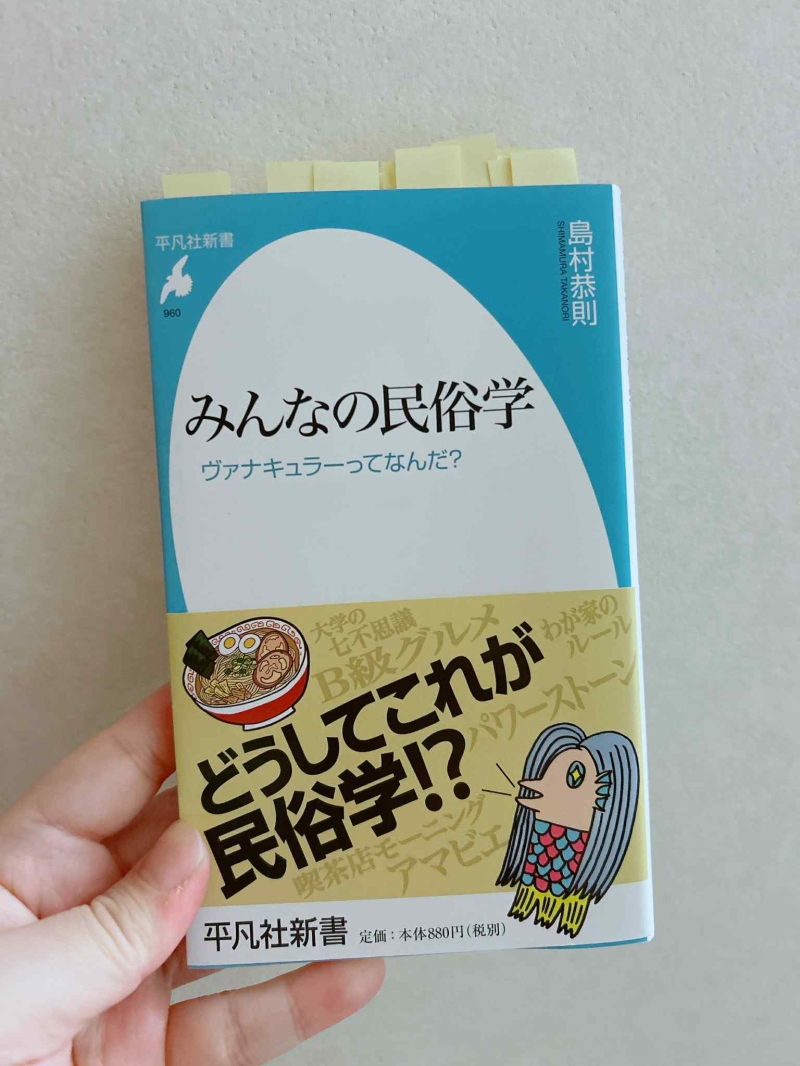
あなたの家のルール、もしかしたらヴァナキュラーかもしれません
9月の本(新書を読む)
怪しい話が好きである。先日3年間、積読から読破した本は、柳田國男や折口信夫が狂言回しに登場する、民俗学をベースにした妖怪やUFOなどが登場するオカルトのライトノベルだった。民俗学と言えば、日本古来の、辺鄙な田舎にある、謎に包まれた神秘!っと思い込んでいたが、どうやらそれが全てではないらしい。
『民俗学とは、過去を用いた現代学。現代を知るための手段として過去を参照しているのであって過去の解明自体を目的としているわけではない。』と記述がある。日常にあるルール、習慣、文化が出来た背景を知るために過去を参照する。本書の構成も、日常に潜む独自の文化の例をあげつつ、過去に似た例を提示するという流れになっている。また本書では、本来民俗学的なセンテンスを示す言葉を「フォークロア」ではなく「ヴァナキュラー」という言葉を使用している。身近な現代民俗学(以下、ヴァナキュラー)、家庭の中、キャンパスライフ、消防士、トラックドライバー、裁判官にも存在するとしている。生活する上で何故か発生した謎のルールや習慣がヴァナキュラーの役割をしているのだ。
例えば、家庭の中のヴァナキュラーとして私は特に面白いと思ったのが「我が家だけのルール」、ある家庭では「探偵!ナイトスクープ」という番組を放送されるたびに家族揃って踊らないと父親に怒られる、というヴァナキュラーが存在する。なんとも奇妙で現代的なヴァナキュラーに驚いて読み進めると、「その家庭の父は、独身時代から第1回目から放送を欠かさず視聴しており、土日休みの金曜日の夜が嬉しいためお酒を飲んでハイになりながら見ていたのが始まりで、結婚後は妻と踊りながら、そして現在は家族そろって週末を過ごせる嬉しさで欠かさずやっている。本人も、子どもができたら受け継ぎたいヴァナキュラーだと話している。
愛のある団らんに、思わず目頭が熱くなった。一生幸せでいてほしい。こういう謎に存在する各家庭のルールもヴァナキュラーとして数えられるならば、私の家で「チョコレートを持ってる人は、おチョコ持ちとして崇め、お恵みをいただく」というのも入るのだろうか。さらに喫茶店モーニングの文化をアジア圏のモーニング文化と比較した章や、B級グルメの起源を探る章もあり、日常生活を掘り下げればそこに必ずヴァナキュラーが存在することが分かる。本書を通じて、物事を見る視野が大きく変わった。ヴァナキュラーは「みんなの学問」である。
『みんなの民俗学 ヴァナキュラーってなんだ?』(島村恭則、平凡社新書、2020年)